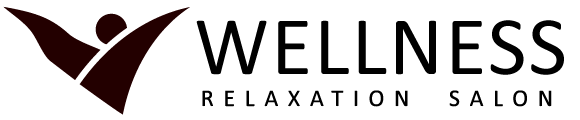6月も後半に入り、蒸し暑い日も増えてきました。
今年もまた、本格的な暑さが続くと
・体がだるい
・食欲がない
・むくみが出る
・眠れない
・イライラする
・頭痛がする
などの「夏バテ」が心配になってきます💦
一言で夏バテと言ってもその原因は一人ひとり異なり、体に現れるサインも少しずつ違います。
今回の健康だよりでは、
『夏バテのタイプと対策』
をご紹介いたします❗️
様々なタイプや、症状が混ざり合っている場合もありますが
今回は特に多い2つのタイプに注目していきます。
①エネルギー不足による慢性疲労タイプ
【胃腸が弱り、体を動かす力が足りない状態】
梅雨〜夏にかけては湿気の影響で胃腸が弱りやすい時期です。
また、冷たい物の摂り過ぎで消化吸収・水分代謝が低下し、だるさやむくみといった不調を引き起こします。
◉ 出やすい症状
✔︎胃もたれ、食欲がない
✔︎倦怠感、元気が出ない
✔︎軟便・下痢気味
✔︎甘いものや冷たいものが欲しくなる
✔︎息切れしやすい
✔︎特に下半身がむくみやすい
◉ 体質傾向
体力があまりない、疲れやすい方。少し動いただけで汗が止まらないことや、雨の日に調子が悪いと感じる方に多く見られます。
◉ ケアのポイント
✔︎常温〜温かい食事を心がける
✔︎甘いもの・小麦製品・乳製品・生ものの摂りすぎに注意(胃腸に負担をかけたり、体を冷やします)
✔︎水分は「冷たすぎないもの」をこまめに摂る
✔︎食後すぐに横にならない(食べ物を消化して、下に降ろしていく力が弱まります)
✔︎満腹過ぎ・空腹過ぎにならないように適度に食事を摂る
《今日からできる食養生》
夏はつい、さっぱりとした麺類を食べたくなりますが
✔︎根菜類(人参、ごぼう、れんこんなど)
✔︎きのこ類(しめじ、しいたけ、えのきなど)
を取り入れると効果的です。
温かく、少しとろみをつけるのがオススメです。(胃腸に優しく、吸収しやすい)
→お粥や雑炊、スープ、蒸し料理など
②熱がこもり、自律神経が乱れやすいタイプ
【熱や血のめぐりが停滞し、自律神経が乱れやすい状態】
東洋医学では、夏の強い陽気やストレスなどが重なると、血を全身に巡らせて精神のバランスを取ったり睡眠を取る力が弱まると言われています。
すると熱がこもった状態になり、心の不安定さや不眠、動悸などを引き起こします。
慢性的な過労や生活リズムの乱れがある方は注意!
◉ 出やすい症状
✔︎イライラ、焦燥感
✔︎寝つきが悪い、夢が多い
✔︎動悸
✔︎顔がほてる、のぼせる
✔︎口内炎や口の渇きが出やすい
◉ 体質傾向
もともとストレスを溜めやすく、感情を内に抱え込む方や、「頭では分かっているのに、気持ちが休まらない」方。また、寝不足やカフェイン過多、夜型生活が続いている場合にも多く見られます。
◉ ケアのポイント
✔︎睡眠時間を整え、心と体も休ませる(夜23時までに就寝が理想)
✔︎深呼吸や軽いストレッチで自律神経を整える
✔︎スマホや強い刺激から少し離れ、静けさを意識する時間を作る
✔︎カフェインや香辛料、アルコールなどは控えめに
《今日からできる食養生》
夏といえば、苦瓜(ゴーヤ)。こもった熱を冷ますはたらきがあります。
夏野菜のきゅうり・トマト・スイカなども潤いを取り入れて体を冷まします。(食べ過ぎると冷えやむくみに繋がるので注意)
また、血の巡りを助ける生姜を少し料理に加えるのもおすすめです!
このように、同じ「夏バテ」でも、原因やケア法が異なります。
「夏になると、毎年体がしんどい」と感じる方は、早めの体質ケアをおすすめします。
夏バテが関係するのは暑い時期だけではありません。
夏バテのまま疲れが積み重なると、
『エネルギーが空っぽ』
『潤い不足で冷えやすい』
状態で、秋に突入することになります。
そして秋にしっかり回復できないまま冬になると、体を温めるエネルギーが不足し、
慢性的な不調(腰痛・頻尿・不眠・疲労感)を招きやすくなります。
また免疫力や回復力が落ち、風邪をひきやすくなることも。
夏に『消耗して回復できなかったもの』が、
冬に本格的な不調として出てくるのです。
冷え性やむくみ、風邪をひきやすい等、冬の寒い時期の不調が気になる人は夏の過ごし方も大切というのは、このような理由です。
ぜひこの機会に、ご自分の苦手な季節や、季節によって出る不調などを思い出してみてください🌿
「特定の季節になると毎年体がしんどい」と感じる方は、長い目で見て少しずつご自分に合ったケアをしていきましょう!
ウェルネスでは、丁寧な体質チェックをもとに、その方に合った施術や生活アドバイスを組み立てて不調を改善していきます。
お気軽にご相談くださいね!